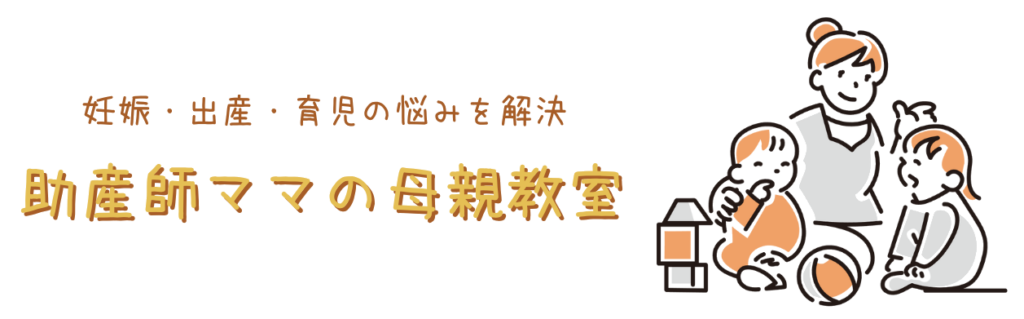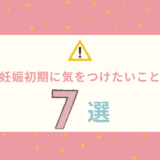出産を終え、病院を退院して、いよいよ赤ちゃんとの新生活がスタート!
しかし、ママの体はまだまだ回復途中。
「どんな生活リズムになるの?」「準備しておくべきことは?」など、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
出産後の生活は、体の回復を最優先しながら赤ちゃんのお世話をする期間です。
この時期は「産褥期」(さんじょくき)と呼ばれ、体調や状況に応じて無理なく過ごすことが重要です。
この記事では、退院後の過ごし方や、快適に乗り切るためのポイントを紹介します。
産後の体の変化

産後、母体にはさまざまな変化が見られます。
子宮が元の大きさに戻るための収縮や、ホルモンバランスの変化が主な要因です。
特に以下のような変化があります。
- 悪露(おろ):出産後の出血で、通常は1カ月程度続きます。最初は赤黒い色から、日がたつにつれて茶色や黄色に変化します。
- 後陣痛:子宮が元に戻る過程で感じる痛みで、特に授乳時に強く感じることがあります。
- 身心の疲労感:新生児の世話は非常に負担がかかり、夜間の授乳やおむつ替えで睡眠不足に陥りがちです。
退院後のママの過ごし方

退院後のママの体は、まだまだ回復途中です。
無理せず、少しずつ新しい生活に慣れていきましょう。
産後2周間目
出産後の最初の1〜2週間は、身体の回復を最優先にし、できるだけ安静に過ごします。
この期間は、授乳やオムツ替え以外の活動を控え、炊事、掃除、洗濯などの家事はなるべく家族に協力してもらい、体を休めることが大切です。
また、お風呂は湯船につからず、シャワーを浴びて体を清潔にしましょう。
産後3周間目
この時期には身体の回復が進むので、簡単な家事から始めて体を慣らしていきましょう。
ただし、無理は禁物です。
短時間の軽作業にとどめてこまめに休息を取りましょう。
赤ちゃんが寝ている時に一緒に横になり、体を休めると良いです。
産後4~5周間目
まだ完全ではありませんが、少しずつ通常の生活に戻り始めます。
日常の家事は疲れたら無理をせず、体調に合わせて行いましょう。
また、1ヶ月検診があるので、必ず受診しましょう。
母体と赤ちゃんの健診で問題がなければ入浴や性生活も可能になります。
産後6周間以降
産後6週間たって経過が順調であれば、職場復帰も可能になります。
ただし、体調と相談しながら進めることが大切です。
また、長時間の遠出は疲れないように注意が必要です。
赤ちゃんのお世話

赤ちゃんのお世話は、授乳やおむつ替え、沐浴が基本です。
授乳
赤ちゃんの授乳は、母乳の場合で2〜3時間ごとに必要となります。
赤ちゃんが欲しがるときに授乳することが大切で、授乳間隔はの赤ちゃんによって異なります。
母乳は赤ちゃんの免疫力を高め、親子の絆を深める役割があります。
初乳は特に栄養価が高く、赤ちゃんにとってとても大切です。
おむつ替え
赤ちゃんのおむつは、おむつかぶれ防止のため、濡れたらすぐに取り替える必要があります。
新生児は1日に6回以上おしっこをすることが一般的です。
沐浴
毎日沐浴を行い、皮膚を清潔に保つことが大切です。
沐浴をする時間帯は、授乳直後や空腹時は避け、午前10時から午後3時頃に済ませることが推奨されます。
沐浴は赤ちゃんのリラックスにもつながります。
退院後の生活を楽にするポイント
家事は手抜きでOK!
出産後は無理をせず体を休めることが大切です。
宅配食サービスや冷凍食品を活用して、食事は簡単に済ませても大丈夫です。
掃除や洗濯は、パパや家族に頼むようにしましょう。
家族やサポートに頼る
2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%で、初めて3割を超え、過去最高を記録しました。
男性の育児休業取得率は近年急速に上昇しており、出産後のサポートを受けやすい環境が整ってきています。
また、実家の家族に産後の手伝いをお願いしたり、里帰り出産で産後を実家で過ごすこともできます。
家族のサポートを受けるのが難しい場合は、産後ヘルパーにお願いする方法もあります。
掃除や洗濯、食事の準備、片づけといった家事全般と、赤ちゃんのおむつ換えや沐浴などの育児サポートをしてもらえます。
悩みを抱え込まない
育児に対する不安や環境の変化に伴うストレスや、出産後のホルモンバランスの乱れから、産後うつのリスクがあります。
できるだけ多く休息を取ったり、家族や友人に相談することが大切です。
1ヶ月健診で気になることを相談することもできます。
まとめ
産後はママの心と体のケアがとても大切です。
必要なサポートを受けつつ、無理なく過ごすことが産後の健康につながります。
少しずつ新しい生活に慣れていきましょう。