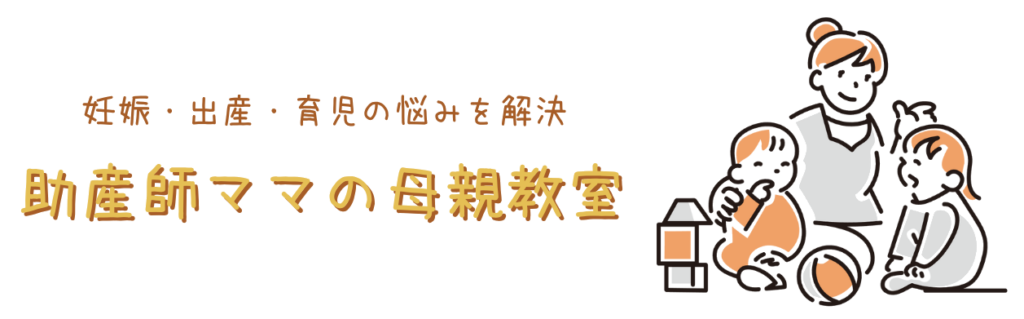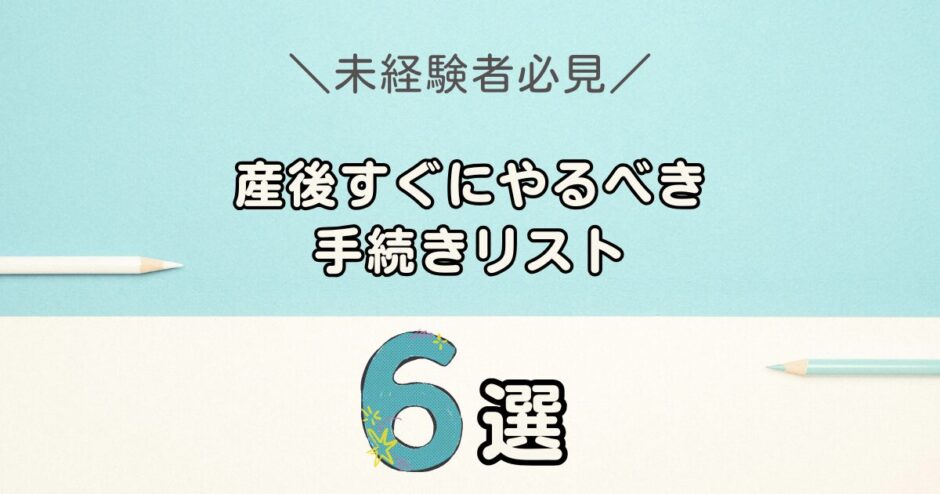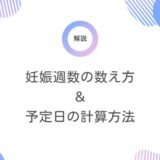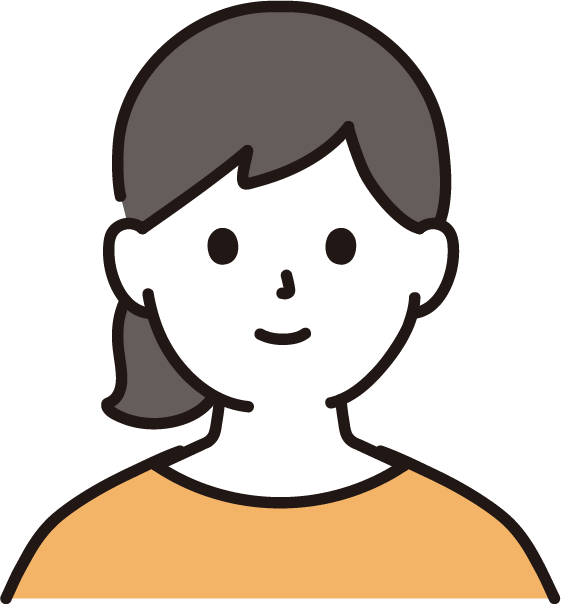
赤ちゃんが生まれました。
出生届の他にも必要な申請はありますか?

出生届の他にもやるべき申請がいろいろあります。
申請漏れをしないためにも、事前にチェックしておきましょう。
出産後は何かとバタバタで忙しくなりますが、必要な手続きもたくさんあります。
出産後にやるべき申請や期限を事前に把握しておくと、スムーズに進めることができます。
結論から言うと、次の6個はおさえておきましょう。
- 出生届の提出・マイナンバーカードの申請
- 児童手当の申請
- 健康保険への加入
- 出産育児一時金の請求
- 乳幼児医療費助成制度の申請
- 育児休業給付金の申請
それでは、出産後すぐにやるべき手続きリストをまとめたので詳細の解説です!
出生届の提出・マイナンバーカードの申請

2024年12月2日以降に出生届を提出されるお子さんのマイナンバーカードの交付を希望する場合、速やかに交付するためにマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになりました。
出生届
お子さんが生まれたの日を含めて14日位内に、お子さんの出生地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出しましょう。
もし海外で出生した場合は、3ヶ月以内です。
出生証明書は、出生した施設で記入してもらいます。
発効までの時間は、平均的に出生後3日以内に発行されます。
早めに出生届が必要な場合は、事前に申し出ると早めに発行してもらえることもあります。
発行された出生届に必要事項を記入して、市区町村役場へ提出します。
出生届の提出場所の市区町村役場によっては、休日や時間外でも届けを受け付けている場合があるので、事前に提出する市区町村役場に確認しておくと安心です。
マイナンバーカード
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」へ移行したことでマイナンバーカードの取得が実質必須となりました。
出生届と同時に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に必要事項を記入し申請することで、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになりました。
申請書は、お住まいの市区町村窓口で受け取るか、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。
なお、医療機関で新様式の出生届を受け取った場合は、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」は不要です。
出生届の提出とマイナンバーカードの申請を同時にすることで、マイナンバーカードが特急発行され、通常よりも早い期間(1週間程度)で自宅へ郵送(簡易書留・速達)されます。
- 出生届(消えるインクを使用したボールペンは不可)
- 母子健康手帳
児童手当の申請

児童手当は0歳から高校生年代までのお子さんを養育している方に支給されます。
支給額は次の表のとおりです。
| 児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
出生の翌日から15日以内に現住所の市区町村に申請することで、翌月分から支給されます。
出生届を提出するタイミングで児童手当の申請も同時に申請するようにしましょう。
- 受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
- 受給者の健康保険証
- 受給者のマイナンバー確認書類
- 受給者の本人確認書類(運転免許証等)

お住まいの市区町村役場に15日以内に申請をしないと1ヶ月分の児童手当が受け取れなくなります。
ママが里帰りをしている場合は、パパに出生届と一緒に児童手当の申請もしてもらうようにしましょう。
健康保険への加入
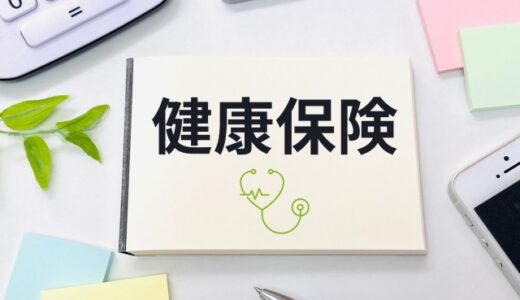
お子さんの健康保険への加入の手続きにはマイナンバーが必要となります。
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」へ移行しました。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることで1週間程度で自宅に郵送されます。
マイナンバーカードが届いたら加入の手続きをおこないます。
手続き方法は、親が加入している健康保険の種類によって異なります。
次に会社員か公務員の場合と、自営業者の場合での手続きについて説明します。
会社員か公務員の場合
親が会社員か公務員の場合、お子さんは扶養する親の健康保険に加入します。
すみやかに勤務先の総務部などの窓口に必要書類を記入して申請します。
自営業者の場合
親が自営業者の場合、お子さんは国民健康保険に加入します。
原則出生した日から14日以内に、母子健康手帳などの必要書類を用意して、現住所の市区町村役場の窓口に申請をします。
国民健康保険の場合は、手続した当日に保険証が発行されます。
出産一時金の請求
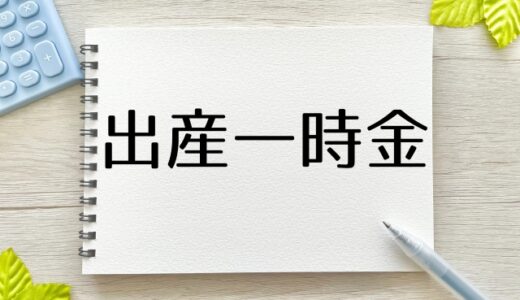
子どもを出産したとき、加入している健康保険の保険者から、1人につき50万円が支給されます。
出産育児一時金を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅するので注意が必要です。
出産育児一時金の請求方法は、次の3つの方法があります。
- 直接支払制度
病院が被保険者に代わって出産育児一時金を健康保険組合に請求する制度です。 - 受取代理制度
出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関等が受け取る制度です。 - 直接請求
出産費用を自分で支払った後に、健康保険に請求する方法です。
直接支払制度と受取代理制度の違いは、直接支払制度が出産育児一時金の請求手続も病院が代行してくれるのに対し、受取代理制度では原則、被保険者が請求手続きをする必要があります。
直接支払制度と受取代理制度は、出産育児一時金の50万円を病院が差し引いてくれるので、出産費用の支払いは50万円を超えた分になります。
もし、50万円に満たなかった場合は、差額分を健康保険に申請をすることで保険者より支給されます。
直接請求は、まず退院時に被保険者が病院へ出産費用を全額支払います。
次に領収書や明細書、代理契約書の写し等を添えて、被保険者が健康保険の窓口へ支給申請することで出産育児一時金を受け取れます。

基本的には、金銭的な負担の少なく手間のかからない直接支払制度がおすすめです。
出産費用が50万円に満たなかった場合は、忘れずに差額の請求をしましょう。
乳幼児医療費助成制度の申請

乳幼児医療費助成制度は、就学前までの乳幼児の医療費の自己負担額を助成する制度です。
受給券の交付には申請が必要です。
申請場所は市区町村役所の担当窓口です。
一部の自治体では郵送や電子申請も可能となっています。
国民健康保険の場合は、手続した当日に発行されます。
- 子どもの健康保険証
- 保護者の本人確認書類
育児休業給付金の申請

雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するするために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の受給を受けることができます。
一定の要件とは、雇用保険に加入している人が次の要件を満たす必要があります。
- 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上)ある月が12ヶ月以上あること
- 育児休業期間中の就業日数が1か月ごとに10日以下(または就業時間数が80時間以下)であること
育児休業給付金を受給するには、必要書類を記入して会社の総務や人事に提出します。
会社側が必要書類をハローワークに提出することで申請は完了です。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
- 母子健康手帳などの写し
- 給付金振込口座の通帳の写し
まとめ
この記事では、産後すぐにやるべき手続きリストとして次の6つを紹介しました。
- 出生届の提出・マイナンバーカードの申請
- 児童手当の申請
- 健康保険への加入
- 出産育児一時金の請求
- 乳幼児医療費助成制度の申請
- 育児休業給付金の申請
出産後の手続きは多いので大変ですが、パパと協力して進めましょう。
児童手当や給付金などのお金に関わる手続きもあるので忘れずに申請をしてください。