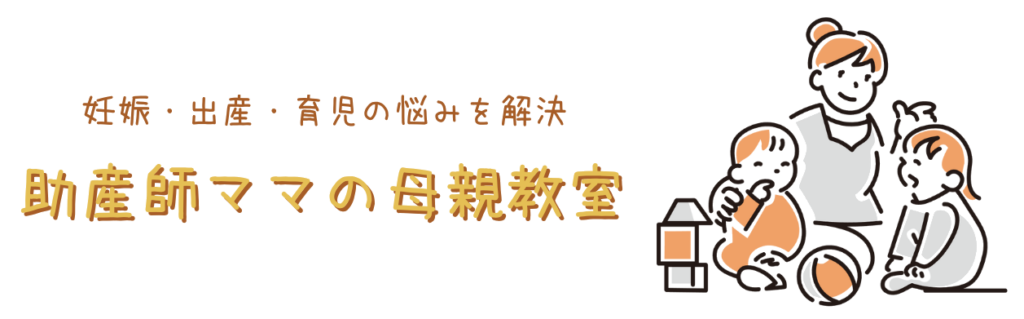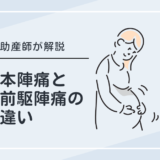「何歳でやるのが正しいの?」
「数え年と満年齢、どっちでお祝いするべき?」
「お参りはいつ行けばいい?」
七五三は、子どもの健やかな成長を祝う大切な行事。
しかし、いざ自分の子どもの七五三を迎えるとなると疑問や不安を持つママやパパは多いはず。
実際、七五三は「3歳・5歳・7歳にやる」と聞いたことがあっても、年齢の数え方やお祝いのタイミングは家庭や地域によって違います。
さらに混雑する時期を避けたり、兄弟姉妹で一緒にお祝いしたりとスケジュールの工夫も必要です。
この記事では、七五三を行う年齢・時期の正しい目安から、数え年と満年齢の違いについて初めてでも迷わないようにわかりやすく解説します。
七五三とは?

七五三は日本の伝統的な年中行事であり、3歳、5歳、7歳の子どもの健やかな成長を祝い、今後の幸せを願って神社や寺院で報告や感謝、祈願を行う「七五三詣」のことです。
その起源は平安時代に宮中や公家で行われていた、子どもの無事な成長を祈る儀式に由来します。
具体的には、3歳の「髪置の儀」(男女ともに髪を伸ばし始める儀式)、5歳の「袴着の儀」(男の子が初めて袴を着用する儀式)、7歳の「帯解きの儀」(女の子が大人と同じように帯を結び始める儀式)が元になっています。
これらは元々別々の儀式でしたが、江戸時代に庶民の間にも広まり、現在のように「七五三」としてまとめて祝われるようになりました。
近年では性別問わず3回すべて行う家庭や、男の子が7歳で、女の子が5歳で祝うケースも増えており、柔軟な考え方が広まっています。
- 3歳:男女両方(髪置きの儀)
- 5歳:男の子(袴着の儀)
- 7歳:女の子(帯解きの儀)
七五三を行う年齢

七五三を祝う際の年齢の数え方には、伝統的な「数え年」と現代で一般的な「満年齢」の二通りがあります。
- 数え年
生まれた時を1歳とし、元日(1月1日)を迎えるたびに1歳を加算する数え方です。 - 満年齢
生まれた時を0歳とし、誕生日を迎えるたびに1歳を加算する数え方です。
七五三は数え年でも、満年齢でも問題はありません。
お子様の成長やスケジュールに合わせて選んでも大丈夫です。
兄弟姉妹で一緒にお祝いするために年齢を調整する家庭も多くなっています。

我が家では、姉妹でタイミングを合わせるために数え年か満年齢かは気にしませんでした。
七五三を行う時期

七五三の正式な日付は、11月15日とされています。
この日付には諸説ありますが、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の長男徳松の健康祈願が11月15日に行われたことや、旧暦の11月15日が二十八宿の「鬼宿日」(鬼が出歩かない吉日)にあたり、収穫を終えて神に感謝する時期と重なったことなどが理由とされています。
しかし、現代では11月15日に厳密にこだわる必要はなく、10月から12月上旬の土日祝日など、混雑や家族の都合の良い日を考慮して選ぶことが一般的です。
特に寒冷地では、11月15日前後は積雪や寒さが厳しくなるため、1ヶ月早めて10月15日に行う地域もあります。
ご祈祷を受ける場合は神社によって事前の予約が必要になるので、事前に確認することをおすすめします。
七五三のながれ
- 着付け・ヘアメイク
自宅、美容院、または写真スタジオで着付けとヘアメイクをします。 - 写真撮影
スタジオでプロのカメラマンに撮影してもらうのが一般的です。出張撮影を依頼したり、前撮りや後撮りをする場合もあります。 - 神社へ参拝
ご祈祷を受ける場合は、社殿に入り、祝詞をあげてもらいます。 - 食事会
家族や親族とレストランや自宅で食事をします。
まとめ
この記事では、七五三の年齢と時期について解説しました。
まとめると次のようになります。
- 七五三は 3歳・5歳・7歳 に行うお祝い
- 年齢は 数え年・満年齢どちらでもOK
- 時期は 正式には11月15日 だが、10月〜12月上旬に行う家庭が多い
七五三はお子さんの成長を祝う大切な日です。
家族の予定やお子さんのペースに合わせて、素敵な七五三を迎えてください。